「せっかく本を読んだのに内容を忘れてしまった…」
「読んだ本の内容をもっと深く理解したい…」
そんな悩みをお持ちのあなたへ。読書メモは、読書体験をより豊かにし、知識を定着させるための強力なツールです。
この記事では、読書メモの重要性から具体的な取り方、活用方法まで完全網羅でご紹介します。読書初心者から読書家まで、今日から実践できるノウハウが満載です。
読書メモを取るメリットと必要性
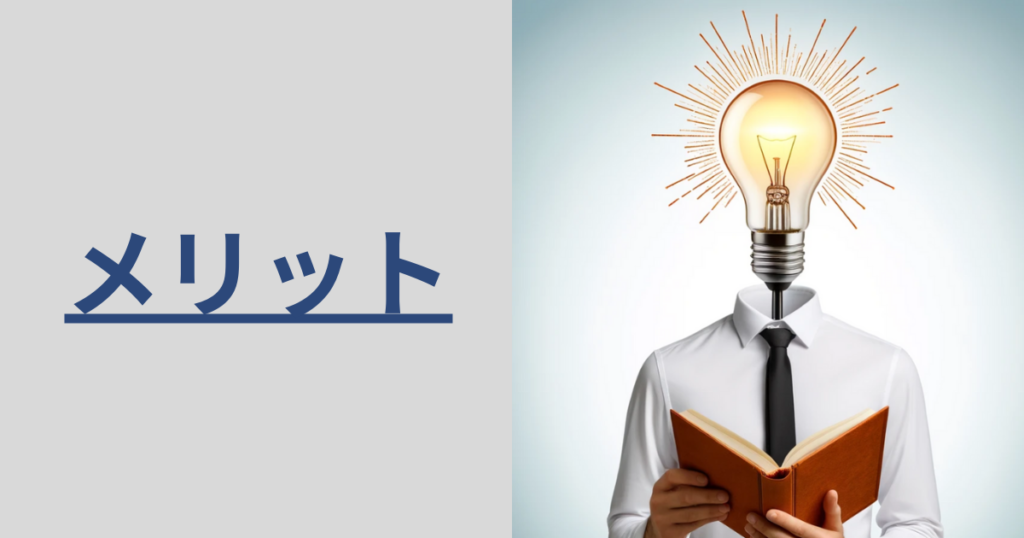
読書メモを取ることで、以下の4つの大きなメリットがあります。
記憶の定着
読書メモを取ることで、読んだ内容を積極的に思い出す作業が発生します。この作業が記憶の定着を促進し、本の内容を忘れにくくします。
知識の整理
ただ情報を鵜呑みにせず、自分の言葉で要約したり疑問を書き留めたりすることで、本の情報に自分なりの「気づき」が加わり、知識が血肉化します。読書メモに自分の考えも残すことで、「本の内容を自分で咀嚼して記憶する」効果が高まります。
必要なときに見返せる
メモを残しておけば、後から「○○について書いてあった本は何だっけ?」という時にすぐ振り返れます。整理された読書メモなら知りたい情報をサッと探せるので、知識を実務で即活用する助けにもなります。忙しいビジネスパーソンにとって、読書メモは後で使える自分だけのデータベースになるのです。
読書のモチベーション向上
メモを取る前提で読むと「この本から何を学ぼう」と目的意識が生まれ、読書体験がより有意義になります。またメモを見返すことで当時の感動や学びを思い出し、「次はこの本を読んでみよう」と次の一冊への意欲も高まります。
忙しくてもできる読書メモの取り方(基本編)

では、具体的にどのように読書メモを取れば良いのでしょうか。ここでは忙しい人でも実践しやすい効果的な読書メモの取り方を、ステップごとに解説します。
1. 読書中:付箋やマーカーでポイントに印をつける
本を読み始めたら、まずは読みながら重要だと感じた箇所に印をつけていきましょう。紙の本であれば付箋や鉛筆での書き込み、電子書籍であればハイライト機能を活用します。
ポイント:初心者の方や「どこをメモすべきか分からない」という方は、一度最後まで通読してから重要箇所にマーカーや付箋を付ける方法がおすすめです。まずは全体を把握してから振り返ることで、闇雲にメモを取って疲れてしまうのを防げます。実際、最初に付箋を貼りながら通読し、後で付箋箇所を中心に読み返してまとめるという方法が一般的です
一方、読書に慣れてきたら読みながら気づいたことを随時メモしても構いません。例えば本の余白に感じたことを書き込んだり、付箋に簡単なメモを書いて貼っていく方法です。本に直接線を引いたり書き込みをしていくと、その本自体が世界に一つのノートになります。
電子書籍の場合もハイライトやメモ機能で同じように記録できます。読了後に「特に大事だ!」と思うポイントだけを別のノートに書き写すつもりで読むと、重要箇所の取捨選択がしやすくなります
2. 読書後:ノートに要点と感想をまとめる
本を読み終えたら、付箋やマーカーを付けた箇所を中心にもう一度ざっと見直し、ノートに要点を整理して書き出しましょう。ここで言うノートは紙でもデジタルでも構いません。大事なのは、自分が「残しておきたい」と思った情報を自分の言葉で書くことです
- 要点を絞る: 全てを書き写そうとする必要はありません。特に印象に残ったポイントや重要だと感じた点を3つ前後に厳選し、それぞれ簡潔にまとめます。抜き書きする場合も、文章をそのまま引用するのではなく自分なりに要約して書くと効果的です。
- 箇条書きでOK: 文章の形でまとめなくても、箇条書きで構いません。箇条書きは後から見返したときに内容を追いやすく、忙しい合間にもサッと読める利点があります。実際、メモの基本は箇条書きにすると良いとも言われます。
- 本の引用も少しだけ: 心に残ったフレーズや後で引用したい名言があれば、ページ番号とともに抜き書きしておくと便利です。ただし引用は最小限にし、「なぜそれが響いたのか」の自分の解釈も添えておくと、より記憶に残ります。
このステップでは読み終えてからできるだけ早くメモを書くのがポイント。
時間が経つと感動や学びの鮮度が落ちてしまうため、可能なら読了直後かその日のうちに取りかかりましょう。忙しくて時間が取れない場合も、箇条書き数行だけでも書いておけば後日肉付けできます。
3. 読書メモのテンプレート例【フォーマット】
読書メモの内容に迷ったら、テンプレート(ひな型)を用意しておくとスムーズです
以下は読書メモの基本フォーマット例です。
- 基本情報: 書名、著者、出版社、出版年(初版年)、読了日
- 要約: 本の内容をひと言で要約すると?(全体像が分かるあらすじやテーマ)
- 心に残ったポイント: 印象的だった箇所や役立つ知識を3つ程度箇条書きで。必要に応じてページ番号や引用も付記。
- 学び・気づき: 本から得た学びや新しい視点、自分の仕事・生活への示唆を書き出す。
- 感想: 読んだ感想や感じたことを自由に(率直な意見や本を選んだ動機との照らし合わせなど)。
例えばビジネス書であれば、「実践したいアイデア」「すぐには使えないけど覚えておきたい知識」なども書いておくと、後から活用しやすいメモになります
また、読んだ本のジャンルによって項目をアレンジしてもOKです。小説なら「好きな登場人物」「心動かされたシーン」などを追加しても良いでしょう。
豆知識:効果的な読書メモ術として教育現場で使われる「KWLチャート」を取り入れる方法もあります。
- K (Know): 読む前に既に知っていること
- W (Want): 読む前に知りたいこと・疑問点
- L (Learned): 読んで新たに学んだこと
この3つの視点で整理するやり方で、実用書や専門書を読む際に有効です。読書前にKとWを書き出して目的意識を持ち、読書後にLを埋めることで「何を得たか」が明確になります。自分の成長を客観的に把握できるので、学習目的の読書メモに取り入れてみてもいいでしょう。
テンプレートはあくまでガイドです。上記の項目を参考に、自分が「これだけはメモしておきたい」という項目をカスタマイズしてください
テンプレートを決めておけば書く内容に迷わずに済み、記録や検索もしやすくなるのでおすすめです
読書メモを充実させるコツ(応用編)
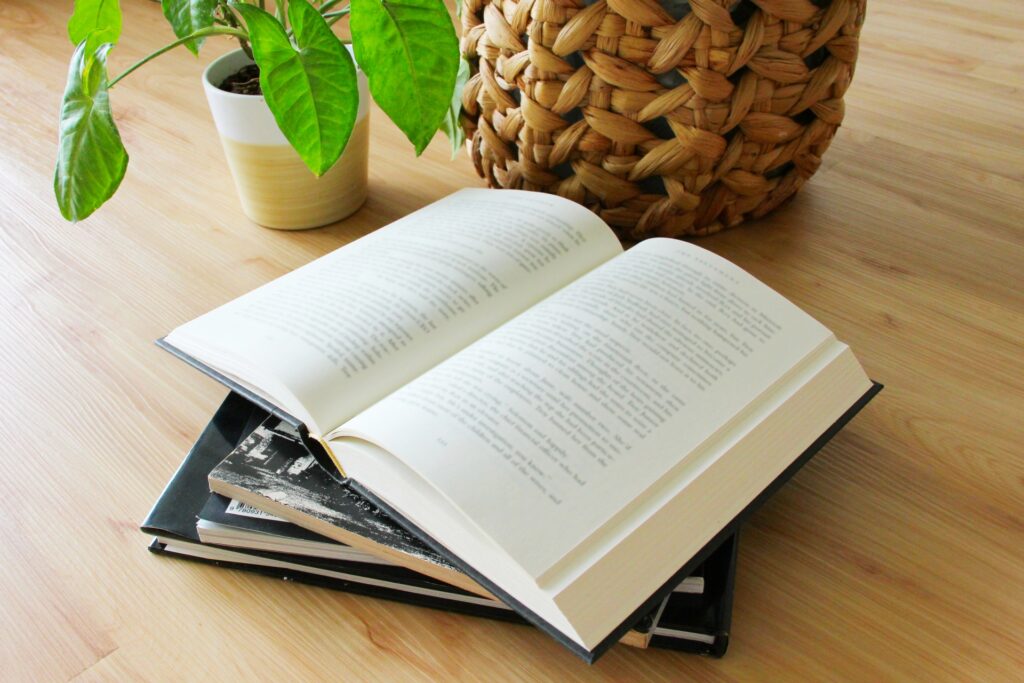
基本的な取り方を押さえたところで、さらに読書メモの効果を高めるためのコツを紹介します。ほんのひと工夫で、メモの質がグンと上がり、記憶への定着率もアップします。
「なぜ?」を書くクセをつける
読書メモでは単に情報を書き写すだけでなく、「なぜそれが重要なのか」「なぜそうすべきなのか」といった理由を添えることを意識しましょう。理由も一緒に書いておくと、後からメモを読み返した際に「ああ、だからこのポイントが大事なんだな」と再び納得できます
たとえば本の中に「毎朝日記を書くと良い」という内容があったとします。それを読書メモに記録する際、「毎朝日記を書くと良い → 朝は頭がポジティブで前向きな振り返りができる時間帯だから」という具合に理由付けまでセットで書くのです。
理由まで書くことで単なる知識が行動に移しやすくなり、読書から得た教えを実践に移すハードルが下がります。書籍もしっかりした内容であれば必ず根拠や理由が書かれているはずなので、そこも含めてメモしましょう
自分の意見や考えも書き添える
本に書かれていた内容すべてに必ずしも同意できるとは限りませんよね。そこで、自分なりの意見や本を読んで感じたことも積極的にメモに残しましょう。
特に本の主張に対して「自分はこう思う」「ここは納得できない」と感じた点があれば、それを書き留めておくことで読書メモは世界に一つだけのオリジナル資料になります
例えば「○○すべきでない」という著者の意見に対し、「※私の考え:私は△△だと感じる。なぜなら…」というように、自分の視点を注釈として追記しておくイメージです
こうすることで単なる要約以上の価値が生まれ、メモ自体が立派なアウトプットになります
実際、読書メモに自分の考察を書き加えていくと、それは一種の読書レビューや感想文にもなりえます。本から得た知識と自分の思考を組み合わせることで、読んだ内容がより深く自分に刻み込まれるでしょう。
継続しやすいスタイルを心がける
読書メモは継続することが何よりも大切です
最初から完璧を目指しすぎると長続きしなくなってしまいます。例えば、凝ったレイアウトで美しく書こうとしたり、色ペンを何色も使ってカラフルに仕上げたりするのは最初は楽しいですが、毎回それをやるのは負担になりがちです。
気楽さ第一!見た目や形式にこだわりすぎず、自分が続けやすいラフなスタイルで始めましょう。
箇条書きと簡単な一言コメントだけでも十分ですし、時間がないときは重要ポイントを1行メモするだけでもOKです。「あとで清書しよう」と思ったメモでも、書いてあるだけで価値があります。逆に綺麗にまとめようとして読書そのものが面倒になっては本末転倒です
また、書くタイミングや量も無理しないこと。理想は前述のように読後すぐですが、忙しい日は無理せず翌日に回したり、全部を書こうとせず途中まででも切り上げたりして大丈夫です。完璧なメモより続くメモを目指しましょう。
形式にとらわれず自由に工夫する
基本は箇条書きや文章でまとめればOKですが、人によっては図や絵で記憶に残るタイプの方もいるでしょう。自由記載欄には感じた疑問や関連アイデアをメモしたり、図解やイラストを描いてまとめても構いません
むしろ視覚的に表現したほうが一目で内容を思い出せるケースもあります。
- イラストの活用: 読後の満足度を星の数で描いてみたり、読んだ後の自分の気持ちを表情アイコンで表現してみると、後から見返したとき当時の感情が直感的に蘇ります。小説なら登場人物の相関図を手書きすると物語の理解が深まるでしょう。
- 図解で整理: ビジネス書や専門書では、重要な概念を自分なりに図にまとめると理解が深まります。例えばプロセスをフローチャートにしたり、概念の関係をマインドマップにすると全体像がつかみやすくなります。図解する過程自体が思考整理になり、記憶にも残りやすくなるはずです。
このように、読書メモの書き方に絶対的な決まりはありません
自分にとって使いやすいようにアレンジして問題なしです。大事なのは「自分があとで見て分かりやすいか」「続けられるか」ですから、楽しく工夫しながら自分流のスタイルを確立していきましょう。
まとめ
忙しい社会人にとって、読書メモは読んだ内容を記憶に定着させ、知識を資産化する強力なツールです。ポイントを押さえたメモの取り方を実践すれば、数日経っても本のエッセンスを思い出せるようになり、仕事の現場でスッと使えるようになります。
読書メモを続けるコツは、「頑張りすぎずマイペースに」「自分が楽しい方法で」書くことです。最初は箇条書き数行でも構いません。大切なのは始めることと続けること。
本記事で紹介した方法やテンプレートを参考に、ぜひ今日から一冊、読書メモを取ってみてください。そうすることで、あなたの読書体験は今まで以上に充実したものになるはずです。読書メモを活用して得た知識を仕事や人生に活かし、忙しい毎日の中でも効率よく自己成長を遂げていきましょう!
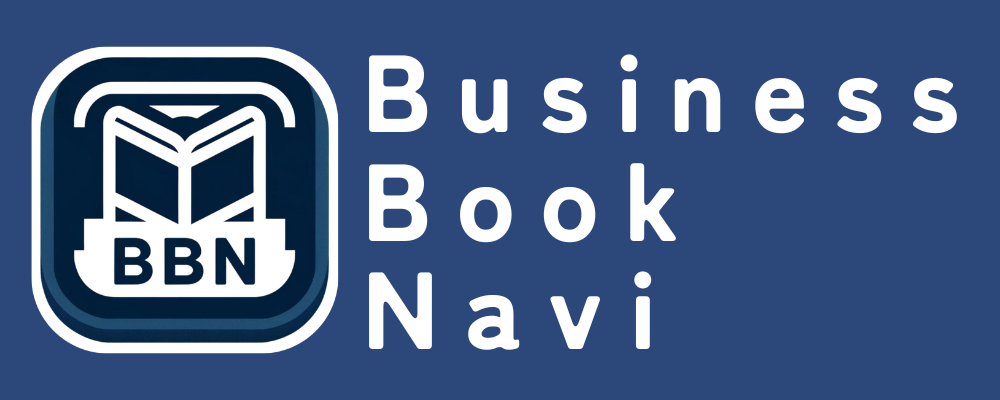
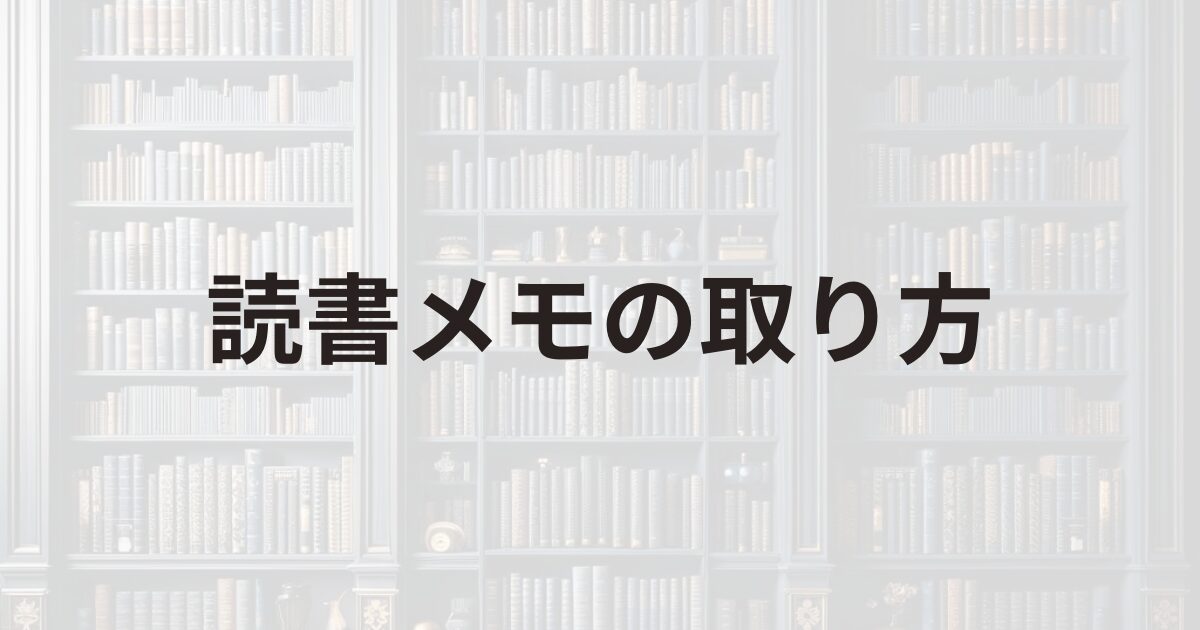
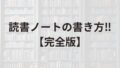
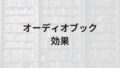
コメント