忙しく働く会社員の方にとって、読書は貴重なインプットの時間ですよね。
しかし本を読んだ内容を、ただ「なんとなく理解した気がする」だけで終えてしまうと、すぐに忘れてしまったり、深い学びにつなげられなかったりすることも少なくありません。
そこでおすすめなのが「読書ノート」をつける習慣です。本記事では、読書ノート 書き方をテーマに、初心者から上級者まで活用できる方法を総合的に解説します。記事を読み終えれば、読書ノートを通じて“本から得た学び”を最大化するコツがつかめるはずです。
読書ノートとは?
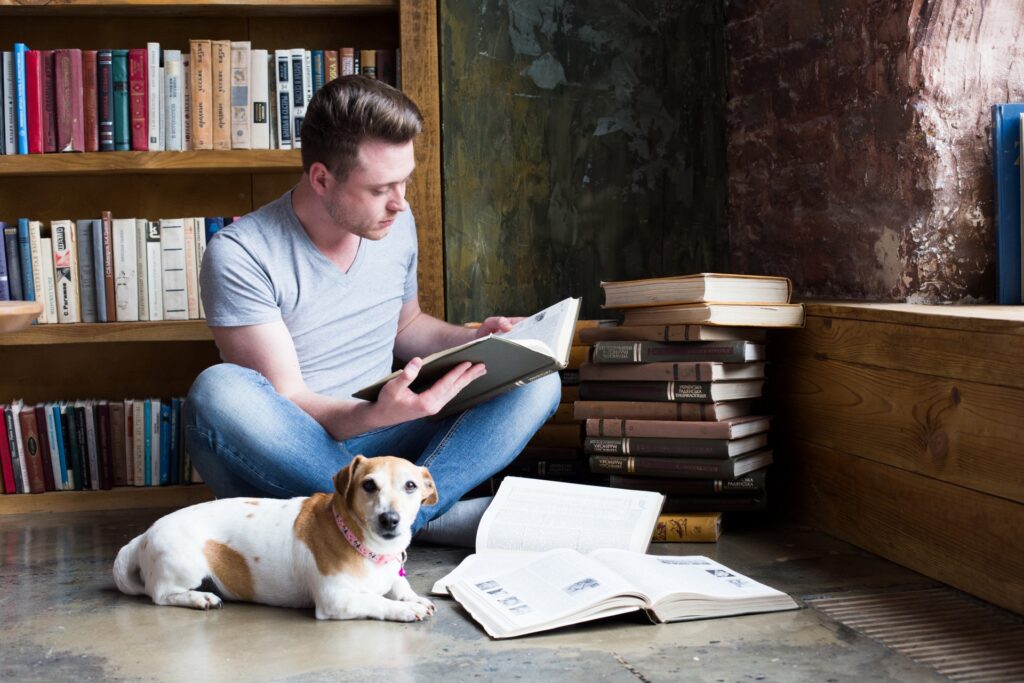
読書ノートの定義
読書ノートとは、読んだ本の要点や感想、学んだことなどをまとめるためのノートのことです。多くの人が学生時代に書いた「読書感想文」をイメージしがちですが、読書ノートは単にあらすじや所感を書くものではありません。むしろ本の内容を自分の頭の中で整理し、行動やスキルアップにつなげるために使う「学習ツール」の一種と言えます。
忙しい会社員であれば、読書に費やせる時間は限られています。そのため、「1冊読んだからOK」と考えがちですが、本来は読んだ後のアウトプットが非常に重要です。読書ノートを書くことで理解が深まり、記憶に定着しやすくなるため、限られた読書時間を有効活用できます。
読書ノートの基本構成
読書ノートには明確な決まった形式はありません。ただし、一般的には以下のような要素を含めると分かりやすい構成になります。
- 書籍情報: 書名、著者名、出版社、出版年など
- 要約: 本で扱われているテーマや主要なポイントを簡潔にまとめる
- 感想・学び: その本から得た学び、自分の意見や気づきを整理する
- 実践アイデア: 読んだ内容を自分の生活や仕事にどう活かすかを考える
このように「書籍情報 → 要約 → 感想・学び → 実践アイデア」の流れで記載すると、後から見返したときにも内容をすぐに思い出せ、アクションにつなげやすくなります。
読書ノートと読書感想文の違い
読書感想文は主に「どのように感じたか」を書くものが中心で、あらすじやキャラクターの心情などをまとめることが一般的です。一方、読書ノートは「得た学びや知識をどう活かすか」をメインとしたアウトプットが特徴です。
- 読書感想文: 文章表現の巧拙、ストーリーの理解や感想、読後の感情を重視
- 読書ノート: 本から得た具体的なインプットを整理し、行動や思考に反映させるためのツール
どちらも読後にアウトプットする点では共通していますが、読書ノートはビジネスパーソンが学んだことを仕事や自己成長に活かすうえで非常に有効な方法と言えるでしょう。
読書ノートをつけるメリット
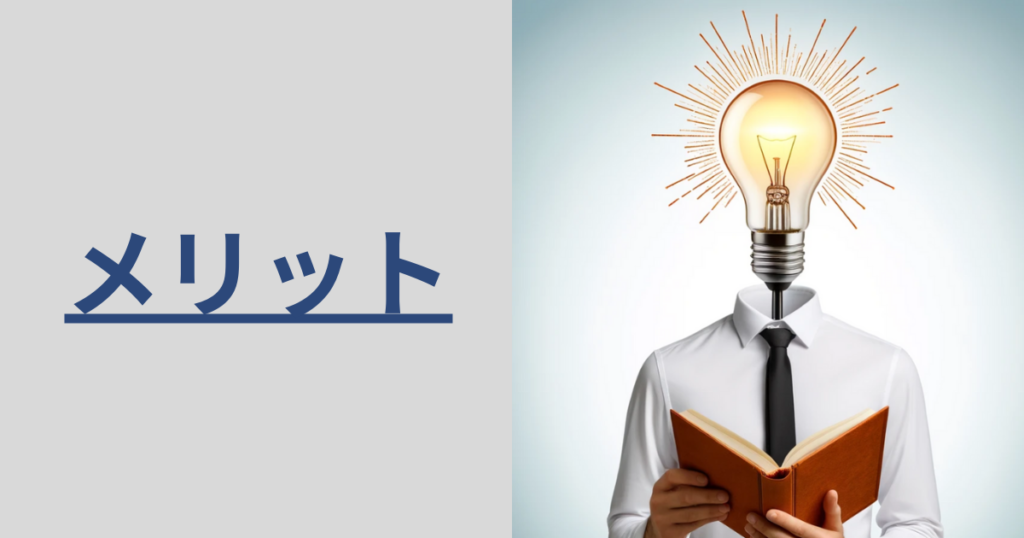
読書ノートを活用するメリットは多岐にわたります。
ここでは主だったメリットを5つほど挙げてみました。
理解を深める
読書中や読書直後に気づいたことを書き出すことで、本の内容を自分の言葉で再構築できます。結果的に「なんとなくわかったつもり」を防ぎ、深い理解につながります。
記憶に定着しやすい
人はアウトプットすることで記憶が定着しやすいとされています。ノートに手書きする、あるいはデジタルツールを使って書き起こすと、脳が処理する情報が増え、内容が長く記憶に残ります。
読書効率の向上
読書ノートを取る前提で本を読むと、「どこに着目すべきか」「何を学びたいのか」を意識しながら読み進められます。結果的に早く、かつ集中して読書を進めることが可能です。
アイデアの発掘
読書ノートには感想だけでなく、自分の考えや関連する他の知識を書き込むことで、新たなアイデアが生まれやすくなります。ビジネス課題の解決策や新規企画のヒントが得られることもしばしばです。
読み返しやすい
読書ノートにまとめておけば、時間が経ってもその本の要点を短時間で思い出せます。「あの本に書いてあったあの重要ポイントは何だったっけ?」というときに非常に便利です。
読書ノートの基本的な書き方

ここからは、初心者でもすぐに実践できる、読書ノートの書き方を具体的に解説します。
本を読む目的を明確にする
読書ノートを書く前に、「なぜこの本を読むのか」「どんな知識やスキルを得たいのか」を明確にしましょう。目的がはっきりしていれば、読書ノートにまとめるべき内容も自ずと見えてきます。
本の基本情報を先に書く
タイトル、著者、出版社、出版年、読了日などを先に記入しておくと、後で振り返る際に便利です。電子書籍の場合は、デバイスや読み方の工夫(メモ機能など)もメモしておくと良いでしょう。
重要な箇所をピックアップしながら読む
「これは大切そうだ」「自分に活かせそうだ」と思った部分は付箋を貼る、ハイライトを入れるなど、読みながらチェックします。あとでノートに転記しやすいよう、印をつけておくと効率的です。
内容を要約する
読み終えたら、章ごとや重要ポイントごとに要約しましょう。要約は自分の言葉で書くのが大切。文字数に制限はないですが、後から見返したときに理解しやすい分量(数行から数十行程度)でまとめると適度です。
感想や気づき、疑問点を記録する
本を読んで「こう思った」「ここは納得できない」など感情が動いた部分を記載します。疑問点や気づきを書き残すことで、後から調べたり人と議論したりするきっかけにもなります。
今後の行動や改善点を整理する
読んだ本をどのように自分の業務や生活に活かすかを書き出すのが読書ノートの要です。具体的な行動例を3つほど挙げるだけでも効果が高まります。
まとめを書く
最後に、本全体を通じて感じたことや総評をまとめると、内容がさらに整理されます。数行でもよいので、最終的なまとめ欄を作っておくと良いでしょう。
読書ノートのテンプレート
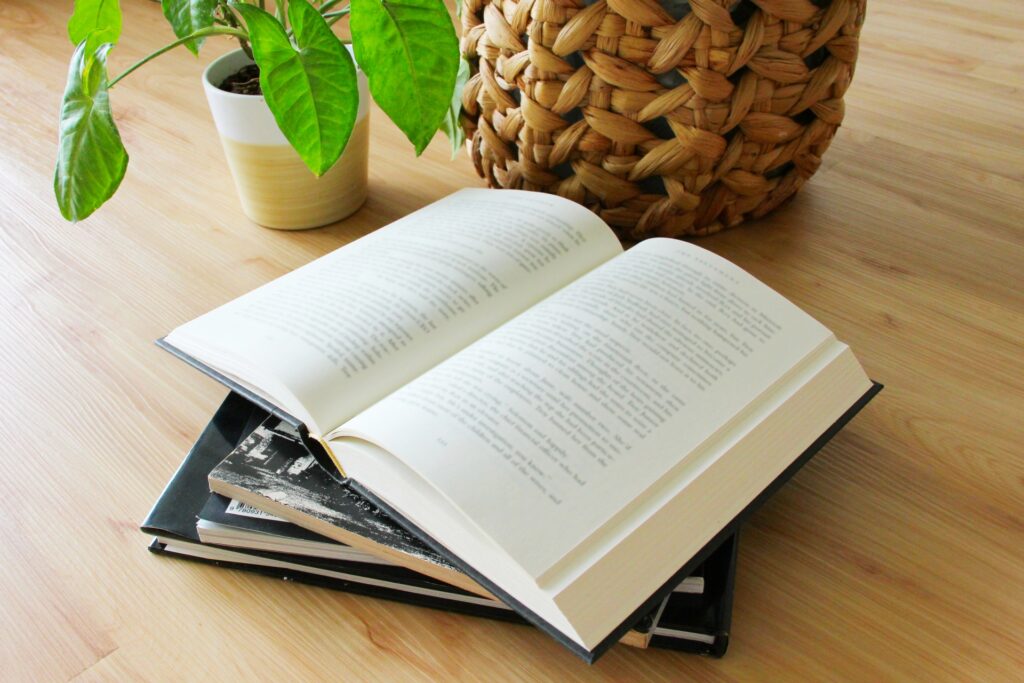
読書ノートを作るときのテンプレート例をいくつかご紹介します。どれか一つを選んでもよいですし、自分好みにミックスしてカスタマイズしても構いません。
ブックリスト形式
簡単な記録方法
- タイトル、著者名、読了日、評価(星の数など)を記録するだけのシンプルな形式です。
- 読書量を把握したり、おすすめの本を人に紹介したりする際に便利です。
# タイトル: __________________________
# 著者: __________________________
# 出版社: __________________________
# 読了日: __________________________
## 一言感想 – _______________________________________________
コモンプレイス・ブック形式
詳細な記録方法
- 読んだ本の内容をテーマ別に分類し、関連する情報をまとめて記録する形式です。
- アイデアの整理や発想の促進に役立ちます。
# タイトル: __________________________
# 著者: __________________________
# 出版社: __________________________
# 読了日: __________________________
## 気になった箇所の引用
– 「_______________________________________________」
– 「_______________________________________________」
## 感想・考察
– _______________________________________________
– _______________________________________________
## 今後の活用方法
– _______________________________________________
– _______________________________________________
詳細な読書ノート
本格的な記録方法
- 基本情報、要約、感想、引用、考察に加えて、キーワード、関連書籍、参考文献などを記録する詳細な形式です。
- 研究や論文執筆など、より深く本を理解したい場合に有効です。
# タイトル: __________________________
# 著者: __________________________
# 出版社: __________________________
# 読了日: __________________________
## 気になった箇所の引用
– 「_______________________________________________」
– 「_______________________________________________」
## 感想・考察
– _______________________________________________
– _______________________________________________
## 今後の活用方法
– _______________________________________________
– _______________________________________________
読書ノートを続けるコツ

実際に読書ノートをつけ始めてみると、最初のうちは意欲的でも、忙しさにかまけて続かなくなることがあります。ここでは継続するためのいくつかのコツを紹介します。
無理な目標を立てない
たとえば毎日1冊読もうとしたり、毎回詳細に書き込もうとしたりすると、挫折しやすいです。まずは「週に1冊」「簡単な要約だけ」など、ハードルを低めに設定しましょう。
読む本のジャンルを広げる
読書ノートが続かない原因のひとつは、同じジャンルばかり読むことで飽きてしまうことです。ビジネス書に加えて、小説やエッセイ、自己啓発書、趣味関連の書籍など、さまざまな分野に手を伸ばすと刺激が得られます。
時間を決めて書く
「朝の通勤電車の中で15分だけ」「就寝前に10分だけ」といったように、読書ノートを書く時間をルーティン化すると、継続しやすくなります。スケジュールに組み込むイメージで取り組むと◎。
デジタルツールを併用する
紙のノートが苦手な人は、スマホやタブレットを使ったメモアプリや読書管理アプリが便利です。クラウド同期でいつでもどこでも書き込めるため、日々忙しい会社員でもスキマ時間を有効活用できます。
読んだ後すぐにノートを取る
人の記憶は時間が経つほど薄れていくもの。読了後すぐにノートを取る習慣を身につけると、印象が鮮明なうちにメモが取れ、書くこと自体のハードルが下がります。
読書ノートの活用方法

読書ノートは書くだけではもったいないです。せっかくまとめた内容をフルに活かすためにも、活用方法を知っておきましょう。
プレゼンやレポート作成の参考資料に
仕事でプレゼンやレポートを作成するときに、読書ノートの要約や引用をそのまま活かせます。必要な情報を効率的に探せるように工夫しておくと便利です。
勉強会や読書会のネタに
同僚や友人と読書会を開く際に、読書ノートの内容を共有すると議論が深まります。自分とは異なる視点や感想に触れると、新たな発見があるでしょう。
自己分析やキャリア設計に活かす
読書ノートを蓄積していくと、自分が関心を寄せるテーマや価値観の傾向が見えてきます。どんなスキルを伸ばしたいのか、キャリアをどう形成したいのかを考える上でのヒントになるかもしれません。
SNSやブログ発信の素材に
読んだ本の内容をSNSやブログで発信したい場合に、読書ノートのまとめが下書きとして役立ちます。感想や気づきが整理されているので、短い投稿でも要点を押さえた情報発信ができます。
他の資料や知識との紐づけに
読書ノートを取っていると、他の書籍や論文、セミナーで学んだ知識と関連づけやすくなります。タグ付けや分類をしておくと、「Aというテーマを学びたいときはこのノートを見返せばいい」といった具合に再利用が簡単になります。
読書ノートの例と実践
実際にどのように書くか、ざっくりとした例を示します。ここではビジネス書を対象としたケースを想定し、紙のノートに書く場合を例にとってみましょう。
書籍情報
- 書名: 「〇〇〇の教科書」
- 著者: 山田 太郎
- 出版社: ABC出版
- 出版年: 2025年
- 読了日: 2025年2月10日
要約
- 第1章では、現代のビジネスパーソンが身につけるべき問題解決スキルを解説。具体的には「原因分析」「仮説立案」「実行・検証」などの重要性に触れている。
- 第2章では、時間管理の手法とマインドセットについて詳述。特に「1日の最初に優先度の高いタスクを片付ける」「スマホの通知を一括管理する」など、具体例が多い。
感想・疑問点
- 第2章の時間管理術は自分の現状に当てはまる部分が多く、すぐに試せそう。
- 第1章の問題解決スキルについては、すでに他の本やセミナーでも学んでいる内容と一部重複するが、著者独自の視点が新鮮。
- もう少し具体的なワークシートやケーススタディがあると、さらにイメージしやすいのでは?
実践アイデア
- 朝の出勤前に優先タスクを30分取り組むルーティンを始める。
- チーム内で週に1回、問題解決スキルを使ったケース検討ミーティングを実施してみる。
- スマホの通知を限定して、1日2回だけまとめてチェックする。
総括
この本はビジネスの基本を網羅的に学べる初心者向けの教科書的存在。自分の課題である「タスク優先度の管理」を見直すよいきっかけになった。今後は問題解決スキルもチームで共有し、実践ベースで検証していきたい。
このように簡潔な形で記録を残せば、後から参照するときにも要点がすぐにつかめます。
まとめ
読書ノートは、忙しい会社員にとって“効率的に学びを深める”ための強力なツールです。単純に本を読んで終わりにするのではなく、内容を整理し、自分の言葉に落とし込むことで、記憶に定着しやすくなり、仕事や日常に活かせるアイデアが湧いてきます。
もし「読書ノートを書きたいけど時間が取れない」「モチベーションが続かない」という場合は、まずは簡単なテンプレートを使ってみたり、デジタルツールでの管理から始めてみましょう。書いてみると意外と楽しく、思考の整理にも役立ちます。ぜひ、この機会に読書ノートを活用して、新しい学びと自己成長のきっかけをつかんでみてください。
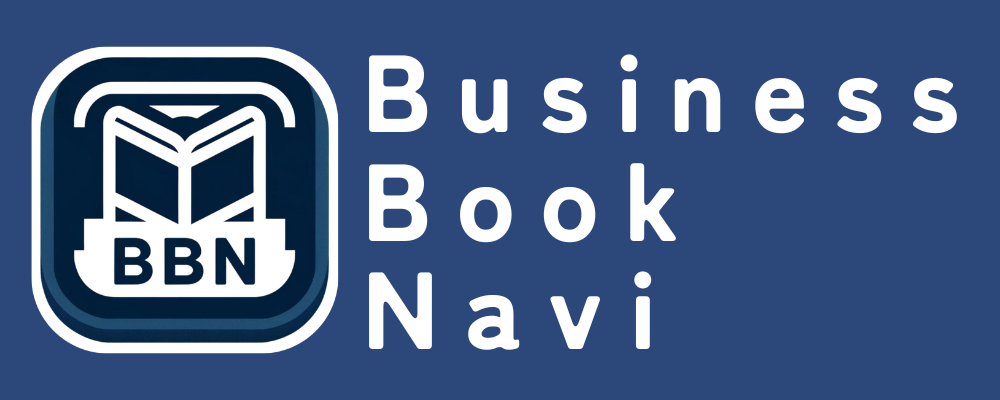
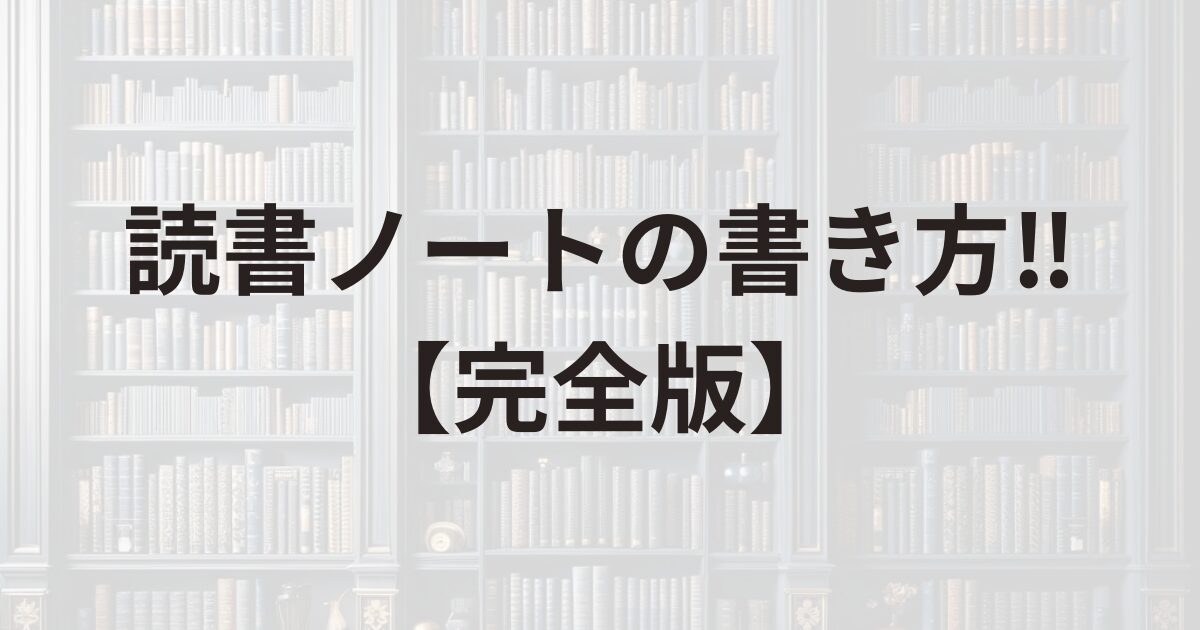
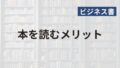
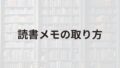
コメント